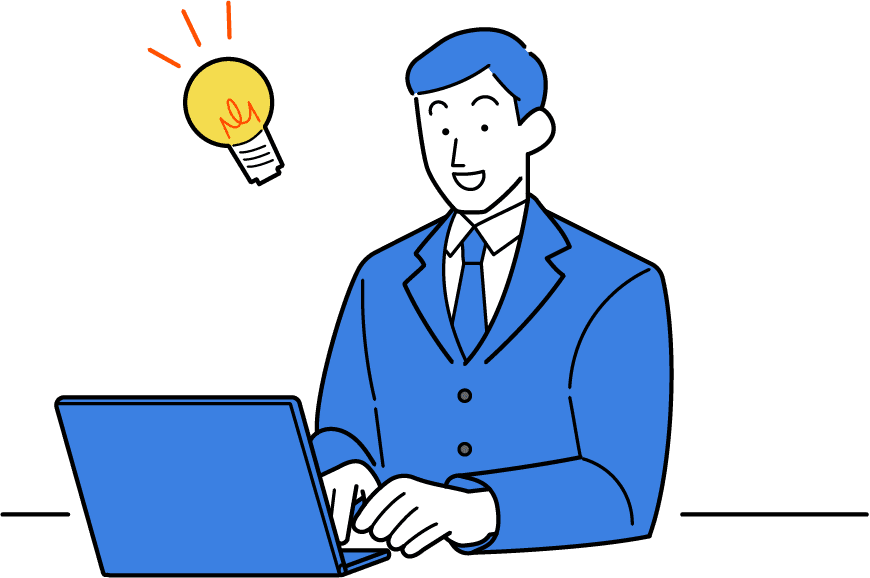海でのドローン活用事例と安全な飛行のための注意点

夏といえば海!広大な海でのドローン活用は、物流の効率化から災害時の救助、インフラ点検、そして海洋環境のモニタリングなど......。活躍の場は広がる一方です。しかし、海でのドローン飛行は、陸上とは異なる特有の課題や注意点が存在します。この記事では、日本で行われている最新の海でのドローン活用事例を紹介するとともに、安全にドローンを飛行させるために知っておきたいポイントを詳しく解説します。
海でのドローン活用事例

近年、技術の進歩によりドローンが海上や水中へと活躍の場を広げ、さまざまな分野で私たちの生活や産業に大きな変化をもたらし始めています。ここでは、ドローンがどのように日本の海で活用され、どのような未来を拓いているのか、具体的な事例を交えながらご紹介します。
海上物流
2024年10月 愛知県西尾市:離島物流「おおあさり」空輸の実証
2024年10月、西尾市の一色漁港と佐久島の間で、新鮮な「おおあさり」などの特産品をドローンで輸送する試みが行われました。この実験で注目されたのは、ルート上に人の配置が不要な「レベル3.5飛行」を約1カ月間にわたって実施したことです。
離島の特産品を新鮮なまま本土へ届けたり、逆に本土から島へ日用品や医薬品を迅速に配送したりと、新たな離島物流の可能性を大きく広げる結果となりました。
参考:chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/540106.pdf
2024年3月 静岡県静岡市・沼津市:医療機器の海上輸送実験
2024年3月には静岡市から沼津市の海水浴場へ、医療機器を積んだドローンが駿河湾を横断して飛行する実証実験も行われました。約30km以上の距離をドローンが飛行し、対岸への緊急物資輸送や医療支援におけるドローンの有効性を示すものです。陸路ではアクセスが困難な場所や、災害時のような緊急を要する場面で、ドローンが人命救助や生活維持に貢献する未来が現実味を帯びてきています。
参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000109780.html
災害時の救助・捜索
2025年2月 神奈川県材木座海岸:海難レスキューの実証
神奈川県材木座海岸では、2025年2月に海難レスキュードローンの実証実験が行われました。この実験では、海流の流れを可視化できるGPS発信機搭載型シーマーカーや、複数の救命浮環を空中投下する装置を搭載した国産ドローンが活用されました。海水浴場エリアで離岸流に流された要救助者を想定し、ドローンがシーマーカーや救命浮環を正確に投下することで、要救助者の早期発見と救助時間短縮、そして救命率向上を目指すものです。
従来の救助活動では、要救助者の発見に時間がかかったり、救助隊員が危険にさらされたりするケースがありました。ドローンを活用することで、広範囲を迅速に捜索し、ピンポイントで救命具を投下できるため、より安全かつ効率的な救助活動が期待されます。
参考:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/prs/r3598926.html
海洋環境モニタリング
2024年度:空海ドローンでカモと共存する地域社会づくり(佐賀県有明海沿岸部など)
佐賀県の有明海沿岸部などでは、養殖海苔へのカモによる食害や羽毛混入が問題となっています。この実証実験では、ドローンでカモの生態調査を行い、水上ドローンを操縦または自動航行させてカモを誘導し、同時に羽毛を回収する手法を検証しています。
海でドローンを飛ばす際の注意点、安全飛行のための重要ポイント

海でのドローン飛行は、陸上とは異なる特別な注意が必要です。
電波干渉対策
海上は陸上よりも電波が届きにくい環境になることがあり、また漁船や船舶が使用する無線との干渉も考えられます。飛行前には必ず電波状況を確認し、不安定な場合は飛行を中止する勇気を持ちましょう。。
航空法と地域のルール遵守 申請の有無を確認する
ドローンを海で飛ばす場合も、陸上での飛行と同様に航空法の規制が適用されます。加えて、海上特有の規制や地域の条例にも注意が必要です。
以下のケースに該当する場合は、国土交通大臣の飛行許可・承認が必須となります。
- 人や家屋の密集している地域(DID地区)での飛行: 海岸線近くの住宅地や観光地などが該当する場合があります。
- 空港等の周辺での飛行: 空港やヘリポートに近い海域では、飛行が制限されます。
- 150m以上の高さでの飛行: 高度が高い飛行は許可が必要です。
- イベント上空での飛行: 海上イベントや海水浴場などで人が集まる場所での飛行。
- 夜間飛行: 日没後から日の出前までの飛行は許可が必要です。
- 目視外飛行: ドローンを目視できない範囲での飛行。
- 危険物輸送: ドローンで危険物を輸送する場合。
- 物件投下: ドローンから物を投下する場合。
これらのケースに該当しない場合でも、海上保安庁や地方自治体の条例によって飛行が制限されることがあります。
例えば、漁業区域や特定の港湾内での飛行が禁止されていたり、海水浴シーズン中に飛行が制限されたりする場合があります。飛行を計画する際は、事前に管轄の海上保安庁や地方自治体に問い合わせ、最新の情報を入手するようにしましょう。
強風と急な天候変化への対応
海上は陸上よりも風が強く、また天候が急変しやすい特徴があります。風速計などで必ず風速を確認し、ドローンの最大風速制限を超えない範囲で飛行させましょう。少しでも風が強いと感じたら、無理な飛行は避けるべきです。
突然の雨や霧にも対応できるよう、防水性能の高いドローンを選ぶか、飛行中に天候が悪化した場合に備え、速やかに帰還できるプランを立てておきましょう。
万が一に備える 水没対策とホームポイントの設定
万が一水没してしまった場合に備えて、回収用のネットや釣り竿、ライフジャケットなどを準備しておくと安心です。また、保険に加入しておくことで、機体紛失や破損の際のリスクを軽減できます。
特に重要なのがホームポイント(RTHポイント)の設定です。機体によってはバッテリー残量が少なくなったり、電波が途切れたりすると、自動で設定されたホームポイントに戻る機能を備えているものがあります。
海上での飛行では、離陸地点が船舶上である場合や、波打ち際ギリギリで離陸した場合など、ホームポイントが適切に設定されていないと、ドローンが海上や障害物のない場所へ帰還しようとして水没するリスクが高まります。
必ず離陸前にホームポイントが安全な陸上の場所(できれば高台など障害物の少ない場所)に設定されていることを確認しましょう。また、離陸後もドローンの位置を常に意識し、万が一の際には手動で安全な場所へ誘導できるよう準備しておきましょう。
まとめ
日本における海でのドローン活用は、物流、災害対応、インフラ点検、環境モニタリングといった多岐にわたる分野で目覚ましい進歩を遂げています。愛知県での離島物流や神奈川県での海難救助、国土交通省が進める「海の次世代モビリティ」実証事業など、その事例は枚挙にいとまがありません。
しかし、海でのドローン飛行は、電波干渉、急な天候変化、水没といった陸上にはない固有のリスクを伴います。
これらのリスクを十分に理解し、航空法や地域の条例を遵守し、事前の準備と適切なホームポイントの設定を行うことで、安全なドローン運用に繋がります。
ドローンに関わるあなたへ、もっと役立つ情報を。
HI-ZEN DRONE SCHOOLのメールマガジンでは、国家ライセンス制度の最新情報や、DIPSの申請変更点、現場で役立つテクニックなど、
ドローン活用に関する"実務直結の情報"をお届けしています。
お役立ちコラムの更新情報だけでなく、
- 法改正の速報
- 受講生限定の講習会・体験会情報
なども、タイムリーに発信中!
こんなあなたにおすすめ
- ドローンを業務で使っているが、制度がよく分からない
- 国家資格に興味はあるが、今すぐではない
- HI-ZEN DRONE SCHOOL 主催イベントに参加したい(オンラインイベントもございます)
メルマガ登録フォームはこちら。
お名前とメールアドレスを入力するだけで登録が完了します。